
 国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内に住む20歳から60歳までの方は、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。 やがて訪れる長い老後や、思いがけない病気や事故などで障害が残り働けなくなったときなど生活の安定を損なうような「万が一」に備え、保険料を出し合いお 互いを支えあう大切な制度です。
国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内に住む20歳から60歳までの方は、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。 やがて訪れる長い老後や、思いがけない病気や事故などで障害が残り働けなくなったときなど生活の安定を損なうような「万が一」に備え、保険料を出し合いお 互いを支えあう大切な制度です。
20歳になったら、すでに厚生年金や共済年金に加入している方を除き、成人の責任として忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう!
なお、学生の方には、在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる「学生納付特例制度」、所得が少なく保険料の納付が困難なときには、「納付猶予制度」、「保険料免除制度」がありますので、未納のままにせずお早めに手続きをしてください。
| ○ 入ります |
○ 入ります |
○ 入ります |
× 入りません |
| ○ 入ります |
○ 入ります |
○ 入ります |
× 入りません |
| × されません ※ |
× されません ※ |
○ されます |
× されません |
※受給する年金額を増やすには保険料を追納する必要があります。
| 20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業・自由業・学生・フリーアルバイター・無職の人など |
| 国民年金は自分で納めます。 |
| 市町村の国民年金担当窓口で加入手続きをします。 |
| 厚生年金に加入している会社員、公務員など |
| 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれるので、自分で納める必要はありません。 |
| 勤務先が加入手続きをします。 |
| 20歳以上60歳未満の厚生年金の加入者に扶養されている妻(夫) |
| 国民年金保険料は、自分で納める必要はありません。配偶者の加入している厚生年金や共済組合が負担します。 |
| 配偶者の勤務先が加入手続きをします。 |
| ・日本国内に住む60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない場合)。 ・20歳以上65歳未満の外国にいる日本人 ・65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格が不足する人で、70歳未満までの間で老齢基礎年金の受給要件に達するまで(ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人に限ります。) |
| 市町村の窓口で加入手続きをします。 |
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。
※納めた保険料は、年末調整確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。ただし、社会保険料控除証明書(または領収書)の添付が必要です。
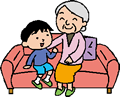 日本年金機構から送付された納付書により、銀行、郵便局、農協、信用金庫、コンビニエンスストアなどで納める方法と口座振替による方法があります。
日本年金機構から送付された納付書により、銀行、郵便局、農協、信用金庫、コンビニエンスストアなどで納める方法と口座振替による方法があります。
※クレジットカードで納めることもできます。希望される場合は塙町役場町民課へお問合せください。
| 68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方 :年額816,000円(令和6年4月からの年金額で満額受けた場合) 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方 :年額813,700円(令和6年4月からの年金額で満額受けた場合) |
| 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受けることができます。ただし、年金を受けようとす る年齢により一定の割合で減額されます。いったん繰上げ支給を受けると65歳以後もずっと同じ割合で減額されます。また、66歳以降に繰下げて支給を受け る場合は、年金を増額して受けることもできます。 |
国民年金加入中に病気やけがで一定の障害が残ったときや、20歳前の病気やけがで一定の障害が残った場合などに支給される年金(※子とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害のある子の場合。)
|
1級障害:68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方・・・816,000円×1.25+子の加算 |
| ・初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)の属する月の前々月までの保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上であること。(保険料の免除期間や学生納付特例期間などを含む。) ・初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合 |
国民年金の加入中や老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、生計を維持されていた「子のある妻」、または「子」に支給される年金。(※子とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害のある子の場合。)
| 68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方・・・816,000円+子の加算 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方・・・813,700円+子の加算 ※令和5年度の価格で年額 |
| ・死亡日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上あること。(保険料の免除期間や学生納付特例期間などを含む。) ・死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合 |
国民年金や年金制度について、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
・日本年金機構ホームページ(新しいウインドウで開きます)
電話番号:0247-43-2114 ファックス番号:0247-43-2137